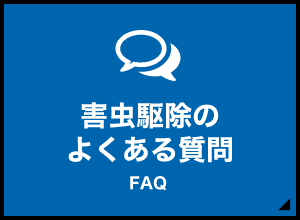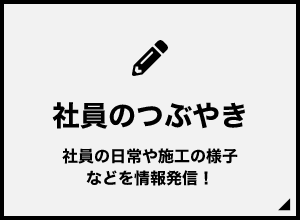主な小動物の侵入源
2024-10-01
カテゴリ:ネズミ
近年、一般家庭やアパート住まいの方からの
ネズミの問い合わせ及び駆除依頼が大変多くなっております。
そのネズミの侵入経路と成り得るケースの一つを紹介します。
涼しくなる9月から11月ころにかけてがネズミのお問い合わせのピークです。
気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
(技術部 K.A)
街中にオオスズメバチの脅威!
2024-09-16
カテゴリ:ハチ,毛虫,アメリカシロヒトリ
9月も中旬を過ぎましたが、まだまだ残暑が続いています。
季節の虫たちもいっそう活発です。
この時期はとにかくスズメバチの巣が最盛期を迎え、
駆除のご依頼も非常に多くなっています。
今回は技術部の私が実際に駆除作業を行ったいくつかの事例をご紹介します。
3件目、今回最後にご紹介するのはやはりこの時期にピークを迎える毛虫!アメリカシロヒトリです。
梅の木にクモの巣のような糸を張っているのがわかりますか?これがこの毛虫の特徴です。小さいうちはこの糸に守られながら集団で過ごしています。成長するとここから離れ、葉っぱを食べながらどんどん周囲に広がっていきます。時には桜の木を丸裸にしてしまうことも。。
梅の木にクモの巣のような糸を張っているのがわかりますか?これがこの毛虫の特徴です。小さいうちはこの糸に守られながら集団で過ごしています。成長するとここから離れ、葉っぱを食べながらどんどん周囲に広がっていきます。時には桜の木を丸裸にしてしまうことも。。
今年はこの猛暑の影響でハチが少ないとの報告もあるようですが、
当社には例年以上のお問い合わせをいただいております。
秋のスズメバチは攻撃性が最も高くなり非常に危険です。
当社はどこにも負けない高い技術力を自負しております。
どんな状況の巣でも、あるいは巣があるかわからなくても、
まずはお気軽にご相談ください。
(技術部 S.A)
秋暑
2024-09-01
カテゴリ:ハチ
8月・9月にお問い合わせが最も多くなる
スズメバチの巣の写真をいくつかご紹介します。
今月の社員のつぶやきは問い合わせの多いスズメバチです。
お客様から『どんなところに蜂の巣ができるの?』とお声をかけてもらう
ケースが多いので、いろいろな所に作ったスズメバチの巣を載せてみました。
写真の他にも天井裏や床下にも作るケースがあります。
この時期からスズメバチは、産卵に専念し、最下部に巣盤を作り新女王、新王を育てます。
巣の規模は大きさ・働き蜂の数ともに最大になり非常に攻撃的になります。
見かけた際はお気軽に当社へご連絡ください。
(K.O)
猛暑
2024-08-16
カテゴリ:ハチ,その他
山形県南陽市。
東北の伊勢と言われる熊野大社で「風の音 ふうりん」を見てきました。願いを込めた短冊を風鈴に吊るす祈願祭も行われていました。猛暑日が続く大変暑い日でしたが、時折吹く風に風鈴の音が涼やかでとても癒されました。
東北の伊勢と言われる熊野大社で「風の音 ふうりん」を見てきました。願いを込めた短冊を風鈴に吊るす祈願祭も行われていました。猛暑日が続く大変暑い日でしたが、時折吹く風に風鈴の音が涼やかでとても癒されました。
これからの時期はスズメバチの巣が急激に大きくなります。
それに伴い行動も活発になり、攻撃性も増して大変危険です。
もし見つけた場合には是非ご相談下さい。
(H.A)
夏の風物詩
2024-08-01
カテゴリ:その他
今年4年ぶりに開催された山形県寒河江市の「さがえさくらんぼフェスティバル」に行って来ました。ミニゲームやフードエリア・マルシェエリア等が展開されていました。中でも毎回注目の「さくらんぼの種吹きとばし」。歴代最高記録地点23.05mに看板が置かれていて、あまりの距離にびっくりしてしまいました。およそ25mプール端から端なので、とても人間技とは思えません。ちなみに私は8m程でした。
スズメバチは8月から活動が最も盛んになる時期に入ります。
大変危険ですので、巣を見つけた際は早急にご連絡ください。
(Y.O)